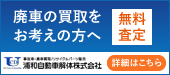タイヤサイズの見方とは?確認方法を解説!
タイヤ交換や買い替えを考えているなら、まずは正しいタイヤサイズの確認が欠かせません。この記事では、タイヤの見方や確認方法、数字や記号の意味、注意すべき法的ルールまでを一つずつ丁寧に解説しています。迷いやすいポイントを押さえて、安心してタイヤ選びを進めましょう。
まずはここをチェック!タイヤサイズの確認方法
タイヤサイズを調べる際には、まず「どこを見ればよいか」「何を確認すべきか」を知ることが大切です。このセクションでは、タイヤ本体や車両ラベル、取扱説明書などを使った基本的な確認方法を紹介します。
タイヤの側面を見ればサイズがわかる
タイヤサイズは、側面(サイドウォール)に刻まれた英数字で確認できます。「205/55R16 91V」のような表記があり、左から順に「タイヤ幅」「偏平率」「構造記号」「リム径」「荷重指数」「速度記号」を意味しています。これは業界で共通のルールに基づいた表記であり、どのメーカーでも基本的に同じ構成です。数字とアルファベットが並ぶため一見わかりづらく見えるかもしれませんが、読み方を知っていれば難しくはありません。
刻印はゴムの上に直接浮き出る形で成形されており、汚れや摩耗で読み取りにくくなっていることもあります。その場合は、乾いた布で汚れを拭き取る、タイヤクリーナーで軽く洗浄するなど、視認性を確保したうえで確認しましょう。
また、タイヤによっては片側にしかサイズ表記がないものもあり、外側から見えない位置に刻まれていることがあります。ホイールの隙間から覗き込む、車を少し前後に動かしてタイヤの向きを変えるなど、工夫して確認するのがポイントです。
タイヤ表記は必ずしも大きく表示されているわけではないため、見落とさないよう全体をゆっくり確認してください。溝の近くやブランド名の周辺に配置されていることもあるため、記載箇所のパターンを知っておくと探しやすくなります。
運転席ドア内側や取扱説明書もチェックポイント
現物のタイヤが確認しづらい場合やもともと装着されていた純正タイヤの情報を知りたいときは、車両に貼られているラベルや取扱説明書を確認してみましょう。多くの車種では、運転席ドアを開けたフレーム部分に、タイヤサイズや空気圧が記載されたステッカーが貼付されています。「前輪」「後輪」ごとにサイズや空気圧が異なることもあるため、表記は細かくチェックしてください。
車種によってはスライドドアの内側や助手席側に貼られている場合もありますが、ラベルの形式は概ね一緒です。貼付位置が見つからない場合でも、車種名+「タイヤサイズ ラベル」と検索すれば、メーカーごとの掲載例を確認できます。
また、取扱説明書には、純正タイヤサイズに加えて、推奨の空気圧やロードインデックス、積載条件に応じた注意点が掲載されています。図解も豊富なので、初めて確認する場合でも理解しやすいでしょう。もし説明書が手元にないときは、メーカーの公式サイトで車名・型式を検索すると、PDF版のマニュアルやスペック情報が確認できる車種もあります。こうした情報を活用すれば、現車確認が難しい場合でも正確なサイズ把握が可能です。
タイヤサイズの構成要素とは?表示の意味を分解
タイヤに刻まれた記号には、幅・高さ・構造・耐荷重・速度といった多くの情報が含まれています。このセクションでは、そうしたサイズ表記が何を意味するのかを項目ごとに整理し、正しい読み解き方を解説します。
断面幅(タイヤ幅)
「205」という数字は、タイヤの断面幅を表しており、単位はミリです。これはタイヤを真横から見たときの最大幅を示しており、205mmであることを意味します。幅が広くなるほど接地面積が増えるため、グリップ力が高まり、特にカーブでの安定感が向上。ただし、タイヤが太くなるぶん回転抵抗も増え、燃費やハンドリングに影響します。
また、ホイールハウスの余裕が少ない車種では、タイヤがフェンダーや足まわりの部品に干渉するケースもあるため注意が必要です。実際に干渉を避けるため、数値だけでなく「車体とのすき間の余裕」を見て判断することもあります。
偏平率(へんぺいりつ)
スラッシュの後に記載されている「55」は、偏平率を意味します。これはタイヤの断面高さが、幅に対してどれだけの割合かを示すもので、「タイヤの高さが幅の55%である」という意味です。例えば幅が205mmであれば、高さは約113mmという計算です。
・計算式
タイヤの断面高さ(mm)=タイヤ幅(mm)×(偏平率 ÷ 100)
・例
113mm = 205mm ×(55 ÷ 100)
数字が小さいほどタイヤの側面は薄くなり、見た目がスポーティになる一方、衝撃吸収力は下がります。逆に数字が大きいタイヤはクッション性が高く、段差や荒れた道でも快適な乗り心地が期待できるでしょう。日常使いの快適性を重視するなら、偏平率が高めのものがおすすめです。
構造記号「R」
「R」は、ラジアル構造を示す記号です。内部のカーカス(骨組み)がタイヤの中心から放射状に配置される構造のことで、現在の乗用車ではほぼすべてがラジアルタイヤとなっています。カーカスが斜めに交差するバイアス構造に比べて、耐久性や乗り心地、燃費性能に優れているのが特徴です。 乗用車向けとして流通しているタイヤはほぼすべてがラジアル構造なので、特別な理由がない限りR以外を選ぶ機会はありません。
リム径(ホイールの大きさ)
「16」は、ホイールのリム径をインチ単位で示しています。リム径が異なるタイヤとホイールを組み合わせられないため、ここは絶対に一致させる必要があります。例えば16インチのホイールには、リム径「16」と表記されたタイヤを選びます。
なお、ホイールのサイズを大きく(または小さく)変える「インチアップ」「インチダウン」を行う場合は、リム径を変更してもタイヤ全体の外径(直径)が大きく変わらないよう、偏平率などでバランスをとらなくてはいけません。さらに、外径が変わるとスピードメーターの表示に誤差が出たり、足回りに干渉するおそれがあるため、慣れていない場合は標準サイズを基準にするのが無難です。
ロードインデックス(LI)
「91」という数値は、ロードインデックス(LI)を表しており、タイヤ1本が支えられる最大荷重を示す指数です。例えば、LI91のタイヤは、標準的な空気圧で使用した場合、1本で約615kgの荷重に対応できます。ただし、実際の耐荷重は空気圧やタイヤの規格によって変動するため、使用条件に応じた確認が必要です。
車種や用途により、指定されるLIは異なります。例えば、ホンダ N-BOX(軽乗用車)はLI75、N-VAN(軽商用車)はLI80が指定されています 。ミニバンやSUVでは、車両重量やグレードによってLI90台後半が指定されることもあります。
荷物を多く積む機会が多い方や、3列シートでフル乗車が多いご家庭などでは、指定されたLIを満たすタイヤを選びましょう。純正より低いLIのタイヤを装着すると、車検に通らなかったり、走行中の安全性が確保できなかったりする可能性があるため、避けてください。
速度記号(スピードレンジ)
最後にある「V」は、速度記号と呼ばれるもので、タイヤが耐えられる最高速度を示します。「V」の場合は、時速240kmまでの走行に対応する性能があるという意味です。これは単なるスピード志向の記号ではなく、タイヤの耐熱性や安定性とも深く関係しています。
一般的なファミリーカーでも「H(210km/h)」や「T(190km/h)」などが採用されており、速度記号が低すぎるタイヤを使うと、性能をフルに発揮できない場合があります。例え普段の運転でその速度域に達しなくても、余裕を持った性能のタイヤを選んでおくことで、走行中の負荷が高まったときにも安定性が保てます。
同じサイズでも違う?XL規格とRFD規格の違い
タイヤには見た目が同じでも、構造や対応荷重に違いがある規格が存在します。ここでは、耐久性を高めた「XL規格」や「RFD規格」がどのような車種・用途に向いているのかを紹介します。
エクストラロード規格(XL)とは
XL規格のタイヤは、内部構造を強化することで、標準仕様より高い空気圧に対応できるようにしたタイヤです。見た目のサイズが同じでも、より大きな荷重に耐えられます。例えば、標準仕様でロードインデックス(LI)が「87」(545kg)のタイヤが、XL規格では「91」(615kg)となることもあります。この性能を活かし、XLタイヤは重量のあるSUVやミニバン、ホイールサイズを大きくするインチアップした車両などに使われています。
一方で、XLタイヤは高めの空気圧を前提としており、標準仕様と同じ感覚で空気を入れると不足するおそれがあります。空気圧が足りないと、偏摩耗や燃費の悪化、乗り心地の低下につながるため、指定値をもとに定期的に確認してください。
レインフォースド(RFD)とは
RFD規格のタイヤは、内部の構造が強化されており、高い空気圧にも対応できるタイプです。この点は、XL規格のタイヤとほぼ同じで、どちらも通常のタイヤより重たい荷物を支えられるようになっています。
RFDという名前は、ヨーロッパの一部メーカーが使っている表記で、日本では同じような性能のタイヤに「XL」という名前が使われるのが一般的です。また、XLが乗用車にも幅広く使われているのに対して、RFDは商用車や荷物を多く積む車に使われるのが一般的です。
どちらを使う場合でも、大事なのは空気圧です。規格に合った性能をきちんと発揮させるには、あらかじめ決められた空気圧を保つ必要があります。
タイヤサイズの選び方は車種と乗り方で変わる
タイヤ選びは見た目やサイズ表記だけでは決められません。車のタイプや使い方によって適した特性が異なるため、用途に合った種類を選ぶことが安全性や快適性にもつながります。ここでは代表的な選び方の考え方を紹介します。
SUVやミニバンは専用タイヤがおすすめ
SUVやミニバンは、乗用車と比べて車高が高く、ボディも重いため、タイヤにかかる荷重やねじれが大きくなります。そうした車種には、専用設計のタイヤを選ぶのが基本です。
専用タイヤは、構造がしっかりしており、コーナーでのふらつきを抑える工夫やトレッドパターン(タイヤ表面の溝のデザイン)による偏摩耗対策がなされています。また、悪路での走破性や荷物を積んだときの安定性も配慮。特に後部に重心がかかりやすいミニバンでは、こうした対策のあるタイヤを使うことで、車体の揺れやタイヤの変形を抑えやすくなるでしょう。
結果として、ハンドル操作に対する反応が安定しやすく、家族を乗せての長距離ドライブなどでも安心して走行できます。
走行距離が長い方にはロングライフタイヤを
年間の走行距離が多い方や、通勤・営業などで毎日車を使う方には、すり減りにくいロングライフタイヤが向いています。ゴムの配合や構造を工夫し、摩耗しにくく作られているため、長く使えて交換の手間も少なく済みます。
製品によっては、雨の日のグリップ力や燃費性能も配慮されており、通勤や買い物などで毎日使う方にとっても、扱いやすい設計です。また、交換頻度が減ることで、タイヤにかかる費用も抑えやすく、維持費が気になる方にも向いているでしょう。
覚えておきたい!タイヤサイズにまつわる法律
タイヤのサイズを変更するときは、見た目や性能だけでなく、法的な条件にも注意が必要です。ここでは、車検や安全性に関わる主なルールを具体例とともに紹介します。
フェンダーからのはみ出し規制
タイヤやホイールがフェンダーの外側にはみ出している状態は、保安基準に違反していると判断されます。前方30度・後方50度の角度から確認した際、タイヤ全体がフェンダー内に収まっていることが必要です。2017年の基準改正以降は、ラベリングやリムガードなど10mm未満の軽微な突出については容認されるようになりましたが、車検場によって判断が分かれる場合もあります。
ロードインデックスの適合
ロードインデックス(LI)は、タイヤ1本あたりが支えられる最大荷重を示す数値です。純正タイヤより低いLIの製品を装着していると、車検に通らない可能性があります。荷重に対して十分な性能が確保されていない場合、バーストや偏摩耗のリスクも高まると考えられています。
スピードメーターの誤差範囲
タイヤの外径を変更すると、スピードメーターに表示される速度と、実際の車速にズレが生じます。平成19年以降に製造された車両では、40km/hの表示時において、実際の速度が30.9〜42.55km/hの範囲内であることが求められています。極端なインチアップや扁平率の変更は、この誤差を拡大させる原因となるため注意が必要です。
車体との干渉と安全性
タイヤのサイズが合っていない場合、走行時にフェンダーやサスペンションへ接触するおそれがあります。このような干渉は構造上の不適合と見なされ、車検で不合格になるだけでなく、走行中のトラブルにもつながるリスクがあります。
タイヤを見直すなら「買取」も選択肢に
タイヤ交換や車の買い替えで使わなくなったタイヤは、そのまま処分せずに売却という方法もあります。このセクションでは、不要になったタイヤを買取に出すメリットや売却時に確認しておきたいポイントを紹介します。
サイズ変更や車の買い替えで不要になったタイヤ
車の買い替えやカスタマイズによって、以前使っていたタイヤが手元に残ることは意外とよくあります。例えば、純正タイヤや、季節ごとの履き替え用として使っていたスタッドレスタイヤなど、しばらく保管したままになっている方も多いのではないでしょうか。
そうしたタイヤでも、溝が十分に残っていたり、比較的新しい年式のものであれば、買取の対象になるケースがあります。特に、軽自動車やミニバン向けのサイズや、商用車用など特定の需要があるタイヤは、思いがけず高値がつくことも。
保管場所に困っていたり、今後使う予定がないタイヤがある場合は、一度査定を依頼してみるのもひとつの方法です。使わなくなったタイヤに、新しい価値が見つかるかもしれません。ただし、安価な輸入タイヤの場合、買い取りが難しい場合があるので注意しましょう。
タイヤ買取でお得に次のタイヤへつなげよう
タイヤの買取価格は、製造年や使用状況、溝の残り具合、保管状態などによって変動します。走行距離が少ないタイヤや、需要の高まる季節前の冬用タイヤなどは、査定額が高くなる傾向です。
「買い替えで余ったタイヤがある」「使わないまましまってある」という場合は、それらを次のタイヤ代に活用できる資源として考えるのもおすすめ。
そのまま保管しておくより、状態が良いうちに売却を検討することで、タイヤをより有効に活用できるでしょう。まずは査定を受けてみることで、新たな選択肢が見えてくるかもしれません。
お見積もりはお気軽にお問い合わせください!

〒338-0824
埼玉県さいたま市桜区上大久保93
TEL 048-854-9923 / FAX 048-855-7848
R京浜東北線 北浦和駅西口より(埼玉大学行き)バス乗車約15分
JR埼京線 南与野駅西口より(埼玉大学行き)バス乗車約10分
「埼玉大学」バス停下車 徒歩約3分